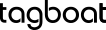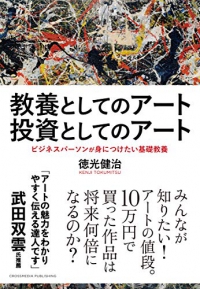インスタ映えするアートとは
今の原宿のギャラリーに入ってみると、ふと「この子、売れそう」と思う作品に出会うことがある。
正確には「この作風」ではなく「このビジュアル」だ。
かわいくて、オシャレで、なんとなく昭和レトロ。
シティポップが背景で流れていそうな、すこしノスタルジックな女の子の絵。
どこかで見たことがある。いや、何度も見たことがある。そう、ある種の“トレンド”である。
もちろんオマージュは悪くない。
が、このシティポップ系のイラストアートは、今や一つのジャンルとして独り歩きし、誰が描いても似たような雰囲気になるという特徴を持ち始めている。
これはまさに、美術界における「アイドル型アート」と呼ぶべきものだろう。
アイドル型アートの特徴は、第一に見た目がすべてであること。
アイドルオーディションでルックスが選別されるように、作品の世界観や思想よりも、まず“映えるかどうか”が問われる。
Instagramにアップしたときに、即座に「いいね!」がつくかどうか。展示空間でフォトスポットになるかどうか。いわば「見た目採用」なのだ。
第二に、その作風は量産が可能である。構図、色彩、キャラクターの表情やポージングに至るまで、ある程度のテンプレートがあり、それをなぞることで“それ風”に仕上がる。
だから多くの作家が似た作品を生み出すことができるし、それがギャラリーやフェアの中で「商品」として並ぶことになる。
ここにプロデューサー的な目線を加えると、アイドル型アートは非常にプロデュースしやすい。
また、今ではこうしたInstagram映えするビジュアルを、生成AIを使って簡単に作り出すことも可能になっている。
見た目で選び、SNSで話題化し、グッズや版画に展開すれば、比較的短期間で利益を回収できる。
作家本人の人生や思想はあまり関係がないし、そもそも誰が作ったかさえ重要ではない場合すらある。
アイドルと同じく“今が旬”であり、“推せるうちに推す”のが正解なのである。
対照的なのが、シンガーソングライター型アートである。
こちらは、まず「どんな世界を描こうとしているか」から始まる。
作風が毎回変わってもかまわない。むしろ変化し続けることこそが作家の魅力とされる。
作品を観るというより、「この人がこのタイミングでこういう表現をした」という一連の流れに意味が生まれる。
技術だけでなく、言葉の強度、コンセプトの深さ、表現の一貫性が評価の対象となる。つまり、見た目よりも“思想の熱量”が問われるのだ。
だから成長にも時間がかかるし、短期的には売れにくい。だが、こうした作家の作品は、10年後、20年後に美術館で再発見されることがある。
アイドル型とシンガーソングライター型、どちらが優れているかという話ではない。
音楽にも一発屋のヒットソングがあり、それに救われる人がいるのと同じように、ビジュアル先行のアートにも価値がある。
ただ、アート市場が「見た目の良さ」と「思想の深さ」を分けて考えず、すべてを“今、バズってるかどうか”で判断しはじめたとき、長く続ける作家にとっては不利な状況が生まれる。
売れたもの勝ちという思想が支配的になると、作品の美術的な価値は急速に瓦解してしまう。
Instagramでの「いいね!」数が作品の価値そのものと直結してしまったとき、本来アートが持つはずの多様な評価軸が失われてしまうのだ。
もしあなたが作家であれば、そしてこれから作品を買おうとする人であれば。短期の熱狂を選ぶのか、それとも長期の対話を選ぶのか。
たとえるなら、それはまるで株式投資のようでもある。アイドル型アートはデイトレードだ。
トレンドの波に乗って、すばやく買ってすばやく売る。瞬発力と話題性がすべてで、情報の鮮度が命である。
一方、シンガーソングライター型アートは長期投資である。
短期的には目立たないが、作家の信頼性や思想、作品の積み上げを見て、じっくりと育てていく。
市場での再評価も時間をかけてやってくる。どちらも一つの投資のかたちだが、目指すものが根本から違っているのだ。
アートは自由である。だが、その自由には選び取る責任もついてくる。
作品の人気度が重要な指標であることは確かだが、それだけになってしまえば、アートはただの流行消費になってしまう。
流行消費とは、タピオカが流行ればタピオカ屋を始めるように、流行に合わせて瞬間的な熱狂を狙い、短期回収を前提としたマスマーケット型のビジネスモデルである。
すでに流行が見えた段階で、いかに早く模倣するかが重要になり、そこに思想や表現の必然性は不要とされる。
評論家の論評、美術史の中での位置づけ、そしてコンセプトの斬新さといった要素は、決して軽視されるべきではない。
そうした多様な物差しの中でこそ、シンガーソングライター型のアートは長く生き続けることができるのだ。
流行に乗ることを前提とせず、自分の表現の芯をぶらさずに時間をかけて育てていく。その姿勢こそが、流行消費とは真逆の、息の長い表現を可能にするのである。
Schedule
- VIP View
4/18 (fri) 16:00 – 20:00Public View
4/19 (sat) 11:00 – 19:00
4/20 (sun) 11:00 – 17:00
- Venue
- 東京都立産業業貿易センター浜松町館 展示場2階
〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝